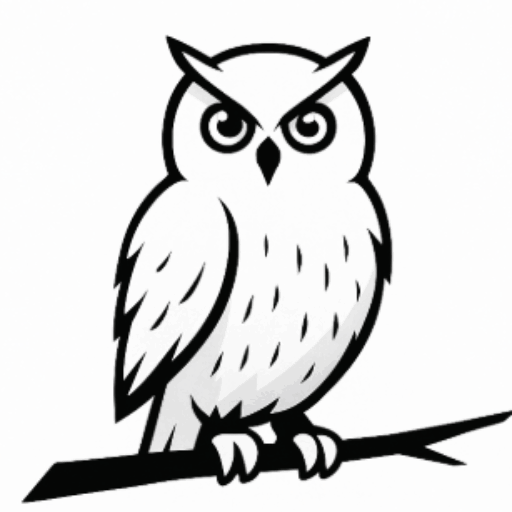賢者は歴史に学び ~先人の知恵と現代の経営者~

本記事は、筆者が2015年以降のコンサルティング業務で出会った実在の企業経営者をモデルにしていますが、プライバシー保護のため、大胆に再構成したフィクションです。特定の個人・企業を指すものではありません。
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」
ドイツの鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルクのこの言葉は、賢明な人は過去の出来事から教訓を学び、自分の経験だけでなく、他者の経験からも学ぶことを意味しています。一方、愚かな人は、自分の狭い経験に頼り、そこからしか学ぼうとしない。
この言葉は、歴史を学ぶことの重要性を説いています。歴史は、過去の人々の成功や失敗の記録であり、そこから多くの教訓を学ぶことができます。自分の経験だけに頼るのではなく、歴史から学ぶことで、より広い視野で物事を判断し、より良い選択をすることができるのです。
活版印刷が開いた知恵の扉
人気漫画でアニメ化もされた『チ。―地球の運動について―』では、天動説から地動説への転換が描かれていますが、そこで極めて重要な役割を果たすのが「活版印刷」です。
活版印刷の発明により、書物が知恵を横方向(地球上のいずれの方向へも)、縦方向(後の世の人へも)に伝播していく様子が見事に描かれています。これこそが、先人の知恵を現代に伝える仕組みなのです。
私は若い頃から本を読むことがとても好きでした。特に読書に没頭していた時期、一冊の本、そして一人の作家との出会いが、私の人間観を大きく変えることになりました。
池波正太郎との出会い
それが池波正太郎との出会いでした。『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』などの作品を通じて、池波正太郎が描く人間観に深く共感したのです。
銀行を辞めて以来、様々な企業でコンサルティング業務を行ってきました。財務体質の改善から組織再編まで、経営の現場に深く関わる仕事です。
この期間で出会った経営者たちを振り返っていると、ある日ハッと気づいたことがあります。彼らは、池波正太郎の作品に登場する人物たちと驚くほど似ているということでした。
白子屋菊右衛門と現代の経営者
あるテクノロジー企業のコンサルティングを依頼されました。その会社は急成長を遂げ、創業社長は短期間で大きな資産を手にしていました。
コンサル開始当初、社長は謙虚で真面目な経営者という印象でした。しかし、コンサルティングを進める中で、徐々に変化が見えてきました。
会社名義での高級車購入、接待費の異常な増加、そして役員の知らないところで進められる社長個人の怪しい投資話。これらの情報が社内で漏れ伝え聞かれるようになりました。私がそれとなく戒めるような助言を行うと、最初は聞く耳を持っていたように見えたものの、次第に私を遠ざけるようになりました。
やがて、この社長は自社株式を担保に借り入れを行い、不動産投資を始めました。私が過度なレバレッジのリスクを指摘しても、「今は好調が続いている」と取り合いませんでした。
その後の市況悪化で、この社長は追加担保を求められ、最終的には保有株式の大半と投資不動産を手放すことになりました。
この社長の姿は、『鬼平犯科帳』に登場する「白子屋菊右衛門」と瓜二つでした。
白子屋菊右衛門は、江戸市中に名の通った大店の主でありながら、裏では凶悪な盗賊団の頭目でした。表向きは米問屋として大成功を収め、町人の信用も厚く、役人からも一目置かれていました。しかし、その裏では金への執着と権力欲に突き動かされ、盗賊の差配や闇商売に手を染めていたのです。最終的にはその欲望が災いし、鬼平に捕らえられ、表の名声も地に堕ちました。
表の成功と莫大な資産、そして会社資産と私物の混同、裏での危険な取引、最終的な金融リスクでの破綻。現代の社長と江戸時代の白子屋菊右衛門は、まさに同じパターンを辿ったのです。
庄司甚内と華やかな業界の社長
コンテンツ関連業界のある会社から財務改善のコンサルを依頼されました。その会社は過去のヒット作品の版権を持っており、業界内でも知名度の高い社長が経営していました。
表面的には華やかな業界で成功しているように見えましたが、内部に入って見てみると、実態は深刻な赤字体質でした。キャッシュフローは常にマイナスで、運転資金も枯渇していました。
私は経営陣に対して、役員報酬の見直しを含む抜本的な経費削減案を提案しました。特に、高額な社長報酬が会社の財務を圧迫している状況を数字で示し、段階的な削減を提案しました。
しかし、社長は「業界での立場もあるし、これまでの功績を考えれば当然の対価だ」と主張し、一切の譲歩を拒みました。取締役会でも同様の姿勢を貫き、私の提案を「現実を理解していない机上の空論」と一蹴しました。
その後、私は契約期間の満了とともにコンサル業務を終了しました。しばらくして、この会社は資金繰りの悪化により経営破綻したと業界紙で読みました。
この社長は『仕掛人・藤枝梅安』に登場する「庄司甚内」そのものでした。
庄司甚内は、表向きは芝居小屋の興行元や人気役者の後援者として「芸事の世界」で名を馳せていました。しかし、裏では多くの借金を抱えながら、贅沢な暮らしと見栄を維持するためにあらゆる手を使って資金をかき集めていました。他人の忠告には耳を貸さず、実際の財務状況とはかけ離れた「成功者」の顔を装い続け、最終的には裏金をめぐるトラブルで命を狙われることになります。
過去のヒット作品という看板、華やかな業界、裏での資金繰り破綻、高額報酬による経費圧迫、忠言の拒絶、そして最終的な破綻。現代の社長と江戸時代の庄司甚内もまた、同じ道を歩んだのです。
猪之吉と搾取する人々
投資会社が運営するサービス業チェーンから組織改善のコンサルを依頼されました。依頼者は、私とは以前から面識のある投資会社の役員でした。
「上場を目指しているので、コンプライアンス体制を整備してほしい」という依頼でしたが、現場を調査すると深刻な問題が山積していました。表面的には黒字を維持していましたが、その実態は従業員への残業代を一切支払わない労働基準法違反黙認に基づく黒字でした。
私は労務環境の改善と適正な労働時間管理の導入、そして未払残業代の支払を提案しましたが、「それでは利益が出ない」「上場スケジュールに影響する」として却下されました。
さらに調査を進めると、投資会社役員と関係の深いコンサルティング会社が、実態に見合わない高額なフィーを受け取っていることも判明しました。法外なコンサル料を受領しているにも関わらず、具体的な成果物や改善提案は見当たりませんでした。
私がこれらの問題を指摘したところ、投資会社役員から「方針に合わない」として契約の早期終了を通告されました。その後、このサービス業チェーンは労働問題で監督署の指導を受け、上場どころか経営破綻したと聞いています。
この投資会社役員は『鬼平犯科帳』の「伊三次の義兄・猪之吉」を思い起こさせました。
猪之吉は、主人公・鬼平の密偵である伊三次の義兄で、表向きは商家に出入りするやり手風の男でした。しかし実態は、抜け目なく搾取的で、弱者を利用し、人の善意や古い縁を「それはビジネスだから」と言って切り捨てる冷徹さがありました。悪事の中心人物ではないものの、利己的で非情、自らの欲を正当化し続けた結果、破滅することになります。
表向きの上場話と利益追求、旧知のコンサルティング会社との癒着と内実での搾取、正論への冷淡な排除、そして最終的な破綻。現代の投資会社役員と江戸時代の猪之吉もまた、同じパターンを繰り返したのです。
人はいつの世も同じように行動する
池波正太郎は、白子屋菊右衛門のような男を「悪人」と断罪しつつも、人間の”欲”の哀しさや滑稽さとして描いています。庄司甚内のような「実力以上の見栄と派手さに溺れた男」を、一種の滑稽な”末期の花”として描きます。猪之吉のような男には「悪人未満の悪人」として、最も冷たい視線を向けながらも、その人間性を深く洞察しています。
長年のコンサルティング経験を通じて、私はひとつの真理に辿り着きました。
人はいつの世も同じように行動する。そこがどこか哀れでおかしい。愛おしい。
江戸時代も現代も、人間の本質は変わりません。成功で変わる人、見栄で破滅する人、縁を利用して搾取する人。フィクションとは言え、池波正太郎が二百数十年前の江戸時代中期・後期を舞台に描写した人間たちと、私が現代のビジネス界で出会った人間たちは、驚くほど似ています。
これこそが「賢者は歴史に学ぶ」ということの意味なのでしょう。歴史は繰り返す、というよりも、人間の行動パターンは時代を超えて変わらないのです。
池波正太郎という先人の知恵に学ぶことで、私は現代の経営者たちをより深く理解することができました。彼らを憎むのではなく、人間の持つ普遍的な弱さや愚かさ、そして哀しさを受け入れることができるようになったのです。
先人の知恵に学ぶということ
先人の知恵は、時を超えて私たちに人間の本質を教えてくれます。
自分の狭い経験だけでなく、歴史に学び、先人の知恵に学ぶこと。それこそが真の知恵であり、ビスマルクの言う「賢者」への道なのかもしれません。
書物を通じて先人の知恵に触れ、人間の普遍的な本質を理解する。そうすることで、私たちは目の前の出来事をより深く、より冷静に受け止めることができるようになるのです。