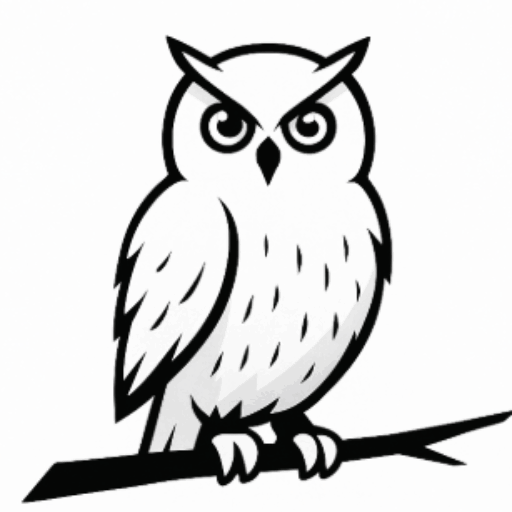敗北から学んだこと ~東大アメフト部での挫折と成長~

「負けた…負けてしまった…」
大学時代を振り返ると、なぜか負けた試合のことばかり思い出します。東大アメフト部での4年間、もちろん勝った試合もたくさんあったのに、悔しさと反省の記憶の方が鮮明に残っているのです。
特に忘れられないのは、4年生最後の試合。1部昇格をかけた決定戦の1週間前、練習中に左膝を負傷。ビハインドの最終盤、逆転タッチダウンが反則で取り消され、僅差で敗北…
その夜の残念会で、涙があふれて言葉にならなかった私。翌朝早く、雪の積もった静寂の中を歩いて帰宅すると、起きてきた母の「ご苦労様」の一言で、また涙が止まりませんでした。
「終わったよ」
まあ、こんな大げさな話をして恐縮ですが(笑)、アメフトで味わった挫折は想像以上に大きなものでした。
今思えば、あの悔しい経験が、今の私の考え方のベースになっているような気がするんです。
2部リーグの現実
東大アメフト部は当時、関東学生アメリカンフットボール連盟の2部に所属していました。簡単に言えば、関東の大学チームを実力順に並べて15位程度の位置。運動部が決して強くない東大の中では「相対的に大したもの」でしたが、やはり私たちが目指していたのは1部でした。
なぜそこまで1部にこだわるのか?
1部には、アメフトの世界を超えて全国区で有名なスタープレイヤーたちがいる。彼らと戦いたい。これはプレイヤーとしての本能でした。
学生日本一を決める甲子園ボウルに出場できるのも1部校のみ。どうせやるなら日本一を目指したい。
そして何より、1部の方がグラウンドが立派で、観客も集まる。自分のプレーをたくさんの人に見てもらいたい。
しかし現実は、土のグラウンドで泥だらけ、怪我だらけの毎日。スタンドはガラガラ。観客は仲間の家族がパラパラと…
それでも私たちは、1部を夢見て、月曜日以外は毎日、フルコンタクトの激しい練習に明け暮れていました。
華やかな1部と、泥だらけの2部。その落差の大きさに、時々心が折れそうになることもありました。
3年時の優勝逃し
そして迎えた3年生のシーズン。戦力も充実し、チームは2部で優勝候補筆頭と呼ばれるまでになりました。ついに1部昇格の夢が現実になる…そう信じていました。
私もレギュラーポジションを掴み、チームの中心選手として期待されていました。練習にも熱が入り、仲間たちとの結束も最高潮。「今年こそは」という思いが、チーム全体を包んでいました。
ところが、2部リーグの最終戦で敗北。あと一歩で手が届くところまで来ていた優勝を逃し、1部昇格も果たせませんでした。
この時の敗北は、私たちの代が最終学年まで一度も1部でプレーできなくなることを意味していました。
正直に言うと、この時「もうアメフトなんて辞めてしまいたい」と思いました。1部でプレーできないなら、やっていても意味がないのではないか。そんな気持ちが、頭をよぎったのも事実です。
でも、後輩たちの顔を思い浮かべるうちに、考えが変わりました。自分の代のような思いをさせたくない。させてはいけない。だからもう一度、自分たちはもう1部でプレーできないけれど、1部昇格を目指して頑張ろう。
そう思えるまでに、実は数週間かかりました。
努力すれば必ず報われるとは限らない。高校時代にも挫折は経験していましたが、チーム全体での挫折は、また違った重さがありました。
4年時最終戦での怪我と敗北
そして迎えた4年生、最後のシーズン。今度こそ1部昇格を果たし、後輩たちに道筋をつけたい。そんな想いで臨んだ最終学年でした。
チームの調子も上々で、再び優勝争いに絡むポジションにつけていました。「今年こそは」という想いが、また胸の奥で燃え上がっていました。
ところが、1部昇格をかけた決定戦の1週間前。練習中の激しいタックルで左膝を負傷してしまったのです。
「痛い…」
倒れ込み、起き上がれませんでした。「やってしまった…」チームドクターに「これまでで一番大事な試合なんです、何とか治してください」と懇願しましたが、返答は「……」。
最も大切な試合に出場できない可能性が高いと告げられました。
信頼するコーチから「試合まで練習に出てこなくていいから、絶対に治せ」と言われ、毎日安静にし、ひたすら完治を祈る1週間でした。
なんとか試合当日には間に合い、スタメンこそ後輩に譲ったものの、途中から出場。
しかし、万全ではない状態での試合。ビハインドの最終盤、逆転タッチダウンが反則で取り消され、僅差で敗北…
またしても、1部昇格の夢は潰えました。
試合後の心境と翌朝のエピソード
試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、何も考えられませんでした。ただただ「終わってしまった…」と。
4年間が、すべて終わってしまった。自分たちの代で1部昇格を果たせなかった。後輩たちに道筋をつけることもできなかった。
その夜の残念会では、仲間みんなで1年間を振り返り、お疲れ様と言い合いました。
そのうち、私は涙があふれて言葉にならなかった。これをきっかけに、みんなも涙で言葉にならなくなった。ただただ「悔しい」、後輩たちに「1部に連れて行けず、申し訳ない」、そんな気持ちばかりでした。
部員全員で集まる最後の会でした。4年生にとって、卒業を控え、もうこのメンバーで集まることは二度とない、そんな気持ちから、夜を徹して飲み語らいました。
いつの間にか雪が降り始めていました。雪は積もり始めていました。翌朝早く、始発を待って最寄り駅に着いた私は、雪の積もった静寂の中を、とぼとぼと20分ほどかけて歩いて帰宅しました。
すると、物音で起きてきた母が一言「ご苦労様」。私は嗚咽しながら母に言いました。「終わったよ」
でも今振り返ると、実は何かが「始まった」瞬間だったのかもしれません。
この経験から学んだこと
あの敗北から数十年が経った今、あの経験が何を教えてくれたのか、今ならはっきりと分かります。
まず、「チームで戦うことの意味」です。一人ひとりの個人の力には限界がある一方、チームになると個人の総和の何倍もの力が発揮されるということ。チームがチームとして力を発揮するには、仲間との信頼が何より大切だということ。そして、チーム全体の目標に向かって、一人ひとりが自分の役割を全うすることの重要性を学びました。
次に、「挫折との向き合い方」です。努力すれば必ず報われるとは限らない。でも、その挫折から何を学び、どう立ち上がるかが人間としての成長を決めるのだと実感しました。
そして最も大きな学びは、「プロセスの価値」でした。結果は確かに大切です。でも、そこに至るまでの過程で積み重ねた経験、培った仲間との絆、自分と向き合った時間こそが、本当の財産だったのです。
これらの学びは、その後の人生やビジネスにおいて、私の根幹となる考え方になっています。
特に、困難な状況に直面した時、あの雪の朝の記憶が、私を支えてくれるのです。
現在への繋がり
今、経営コンサルタントとして企業の皆様とお話しする時、あのアメフトでの経験が、私の土台になっていることを強く感じます。
クライアント企業で「チームがうまく機能しない」という課題に直面すると、まず私が見るのは、メンバー同士の信頼関係です。どんなに優秀な個人が集まっても、信頼がなければチームとしての力は発揮されません。
また、「思うような結果が出ない」と悩む経営者の方々には、「プロセスにも価値がある」ことをお伝えするようにしています。結果だけを追い求めすぎると、かえって本質を見失ってしまう。大切なのは、その過程で何を学び、どう成長するかです。
そして何より、困難な状況に陥った時の「立ち直り方」について、身をもって体験していることが、私の強みだと思っています。
挫折は確かに辛いものです。でも、その挫折から何を学び取るかで、その後の人生やビジネスが大きく変わることを、私は知っています。
あの敗北により味わった強い挫折感があったからこそ、今の私があるのかもしれません。
まあ、こんな大げさな話をして恐縮ですが(笑)、これが私の原点なのです。
終わりに
このように振り返ると、大学時代のアメフトは私にとってとても大きな「学びの場」でした。
技術的なスキルや知識は、後からでも身につけることができます。しかし、チームワークの大切さ、挫折との向き合い方、プロセスを大切にする心構えといったものは、実際に体験しなければ身につかないものです。
もし、今何かに挑戦している方がいらっしゃったら、結果がすぐに出なくても、諦めずに続けてほしいと思います。その過程で得られる経験や学びは、必ずあなたの人生やビジネスの糧になるはずです。
そして、もし大きな挫折を味わったとしても、それは決して無駄ではありません。その挫折から何を学び、どう立ち上がるかが、あなたの真の強さを決めるのです。
私も、あの時の経験を大切にしながら、これからも前に進んでいこうと思います。